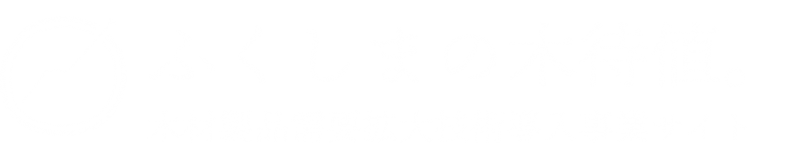株式会社赤井製材所
スギ3層集成ログ材の防耐火試験
令和5年度木材製品需要拡大技術導入事業で実施。
株式会社赤井製材所

営業課長 鈴木柾司
株式会社赤井製作所のホームページ
プロジェクトの概要
3層集成材※をログハウス部材としての実用化に向けて防耐火試験を行い、一般住宅等の市街地でも使用できるように丸太組工法(ログ法)の用途で準耐火性能について認定取得に向け取り組みを行った。併せて、ログハウス販売先・一般工務店等にPR、販売促進を行い、これまでに使用できなかった防耐火地域へ需要拡大を図った。
※集成材:一定の寸法に加工されたひき板(ラミナ)を複数、繊維方向が平行になるよう集成接着した木材製品。

鈴木営業課長に聞いてきました!
ログハウスの特徴
ログハウスは、日本ではあまり一般的ではなく、昔の家の建て方というイメージが強いですが、北欧などでは今なお多く用いられる工法で、研究も進んで進化しています。
ログハウスは、建てるのに必要な材料の種類が少なく、組み立ても容易で1軒1ヶ月程度で完成するなどのメリットがあります。
3層集成材ログ材とは
集成材をログハウスで利用すると重ねた面が見えるため敬遠されてきました。今回の3層集成ログ材は、川の字のようにラミナを貼り合わせることで、ログハウスとしたときに、材の面が自然な感じになります。また、貼り合せる板は大径材から柱を製材して挽き落とされた材なども有効利用できるため、新たな大径材の活用にもなると考えています。

災害時の仮設住宅としても
ログハウスは供給と設置が比較的容易であることから、災害時などの仮設住宅でも使用されます。
赤井製材所では、災害時のためにログハウスを数セット常備していて、令和6年1月の能登半島沖の地震の際には、要請を受け仮設住宅の設置を行いました。
大径材の利用について
元々は、マツの製材を行っており、太い木や長い木を取り扱うことも少なくなかったです。会長は太く大きい木材には価値があるといっており、そういった木材が好きでした。大径材利用は、趣味嗜好から始まったと思います。30~40年前であれば大経材が切り出されてきたときは、いろいろな大きさの部材に製材され日本建築に使われてきました。非常に高価に扱われたため、50年前に植林した人たちは、50年後も同じように材を使えるようにという思いで植林していたと思います。今は我々が想像している以上に、山には大径材が増えています。現在、大径材が安く扱われるようなり、利用されていない現実があるので、次の世代のための植林が行われないのではという不安があります。だからこそ、大径材がしっかり売れる、使っていけるというPRは大事になってくると思っています。