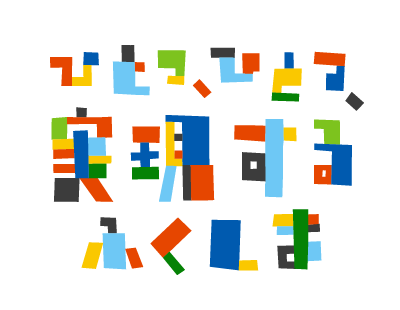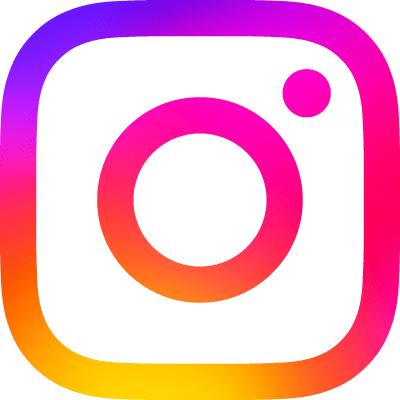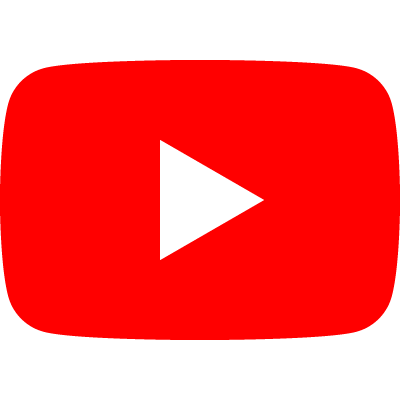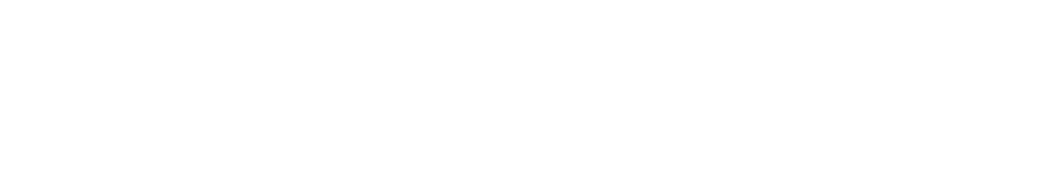
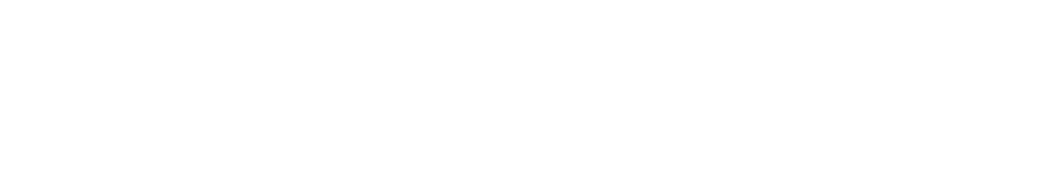
本文
Q&A
項目
技術系学科以外の出身のため、試験を受けるか迷っています。
学生時代に技術系学科以外の勉強をしていたという職員はたくさんいます。業務を行うためには多少、専門的な勉強が必要となることは否めませんが、最近は業務がより多様化しており、職員にも様々な視点や能力が求められている中で、他分野で勉強した内容は逆に強みとなる場合があります。
また、土木職員を対象とした専門研修では、第一線で活躍する大学教員や専門技術者などの外部講師も含め、最新の技術情報や知見を提供するとともに、現場見学や実習を交えるなど内容の充実を図っており、採用後からでも専門的な知識を身につけていくことが可能です。
土木・建築職員として求められる能力はありますか?
土木部で行う事業には、建設コンサルタントや建設会社、市町村、地域住民など、様々な関係者が携わります。事業を進めるにあたり発生する様々な課題に対応するため、これら関係者との調整役として事業を推進していく「マネジメント力」が求められますが、業務を通じて身につけていきます。
なお建築職では、県有建築物の設計・監理や建築確認申請の審査の業務等に従事するため、採用後に一級建築士等の資格を取得することが望まれます。
大学卒程度採用試験のうち、一般枠と先行実施枠の違いを教えてください。
先行実施枠はいわゆる公務員試験のための特別な対策が不要で、かつ一般枠との併願も可能なため、その年の受験機会が2回得られることになります。先行実施枠では、一般枠の教養試験に替えて民間企業でも採用されているSPI3という能力検査を実施。また、一般枠の専門試験に替えて専門性確認シートを作成し、それに基づき個別面接を行います。
受験資格及び試験種目は異なりますが、採用後の職務内容及び勤務条件に差異はありません。受験資格及び試験種目については、各試験の受験案内をご確認ください。
試験場は福島県内のみですか?
大学卒程度(先行実施枠を含む)における採用試験については、第1次試験のみ福島市内のほか東京都内でも受験することが可能です。
高校卒程度における採用試験については、第1次試験のみ福島県内の3会場で受験することが可能です。
民間経験者における採用試験については、令和7年度より、第1次試験を全国各地で受験できるテストセンター方式へ変更となっています。
なお、第2次試験については、いずれも福島県庁での試験実施を予定しています。
民間の会社で働くこととの大きな違いはなんですか?また、公務員の中でも国や市町村との違いはありますか?
<民間との違い>
民間の会社では会社の規模や業種、得意ジャンルによって、ある程度、工事や設計の対象物に偏りが生じ、より専門性が問われることとなります。一方、技術系公務員の場合は、道路、河川、港湾、砂防、都市、建築と多岐に亘る分野に関わり、それぞれ、小規模工事から大規模なプロジェクトまで幅広く携わることとなります。
<国家公務員との違い>
国の職員は、政府で決定された内容に基づき、全国の各自治体で効率的・効果的に事業が展開されるよう、企画や支援を行うことを主な業務としています。一方、都道府県職員の場合は、歴史や風土などの地域特性を踏まえ、県民と一緒になりながら、地域の実情に応じた独自の施策を展開していくことが求められます。施策の立案・実施において、より地域性を踏まえる必要があることと、県民と一緒になって事業を進めることが県職員の業務の特徴となります。
<市町村との違い>
より広域的な視点から道路や河川を整備・管理するところが市町村の仕事とは異なる内容です。また、県内各市町村のバランスを見ながら整備・管理を進めるといったことも県には必要になります。なお、市町村によっては技術系職員が不在の役場もありますので、適切なインフラ整備のために、市町村に対して技術的な支援も行っています。
異動はどのぐらいの頻度でありますか?また、勤務地や所属の希望はどこまで聞いてもらえますか?
土木部に限らず、県の一般職員はだいたい3~4年程度の周期で異なる職場に異動になります。
希望については、採用内定後、調書に希望勤務地、希望部署等を記入し提出することとなっています。また、採用後も毎年同様の調書を提出します。ただし、任命権者は、本人の希望だけでなく、能力や適性、配属の際の欠員の状況等を勘案して配属先を決定するので、必ずしも希望どおりの勤務地や部署等に配属されるとは限りません。なお、異動にあたっては、本庁と出先機関、各任命権者(知事部局と各行政委員会等)間の人事交流も図られます。
女性が働きやすい職場ですか?
仕事内容、配属、昇任などにおいて男女の区別はなく、女性職員も幅広い業務にチャレンジできます。また、出産・子育て支援制度が充実しており、男女問わず、多くの職員が制度を積極的に利用しています。令和5年度の育児休業取得率は、同年に新たに育児休業が取得可能となった女性職員で100%となっており、男性職員も84.1%が取得しています。男性も女性も仕事と育児を両立させやすい職場環境です。
女性職員(土木・建築職)の比率はどのくらいですか?
R6.4.1現在で約6%となっています。